12月5日から6日にかけて、JR高松駅近くの瀬戸内海を見渡すロケーションで「海を望むデックスガレリアから発信! 誰もいないコンサート」が催されました。新型コロナウイルスの影響をまともに受けたアーティスト、そして裏方スタッフに活躍の場をと企画されたこのイベント。

ニュースタンダードを満たす形での公演にこぎつけた裏側には、文化芸術の灯を消さないようにと奔走する、舞台人たちの熱意がありました。イベントの翌週、主催団体のさぬきブルーアクトの事務局長として、中心的な役割を果たした古宇田育代さんに、団体の活動内容や地方における舞台芸術の現状をうかがいました。
舞台芸術に欠かせない「場」の喪失が活動の契機

自身もパフォーマンスカンパニー リトルウィングを率い、ミュージカルやダンスの指導に注力する古宇田さん。今年、結成からちょうど30年を迎えるリトルウィングも記念公演を控えていましたが、コロナ禍を受けて2020年中の開催を断念せざるを得ませんでした。
5月にはスタジオでのレッスンを一時中断。子どもたちにはリモート形式で歌やバレエの課題を出し、個別に練習時間を確保できるよう工夫したといいます。

しかし、舞台芸術に欠かせないのは、成果発表の機会である公演を含む「場」。レッスン生のなかには、母親の車でスタジオの前を何度となく通った子までいました。
6月、スタジオは再開されることになったものの、舞台を踏めない事実は相変わらず。リトルウィングとしては、記念公演の代替イベントを規模を縮小して開きましたが、周囲の芸術団体を見渡してみると、今年中の発表のチャンスがないところも散見される状況でした。

裏を返してみれば、舞台監督や照明、司会をはじめとした裏方スタッフの仕事も激減し、生活そのものに大きな打撃が出ているということ。
演者と裏方、いずれもがダメージを受ける危機を前に、古宇田さんはあらゆる人脈を駆使して、「言い出しっぺ」としてこの難局を乗り切ろうと行動を開始しました。

プロダクションなどに持続化給付金の受給を勧めたほか、クラウドファンディングも検討。ですがここでひとつ、大きな問題が浮上しました。それは「裏方」という呼称からも明らかなように、舞台芸術に関わるスタッフの存在は一般には伝わりづらいということ。
仕事不足にあえぐ裏方スタッフの支援のためには、公的な助成金の受給という手も考えられました。ただし、そのためには具体的な事業を立ち上げなければならないことが判明。つまりは、コロナ禍にも負けない舞台公演をつくり上げる必要があったわけです。そこで、結成されたのがさぬきブルーアクトでした。
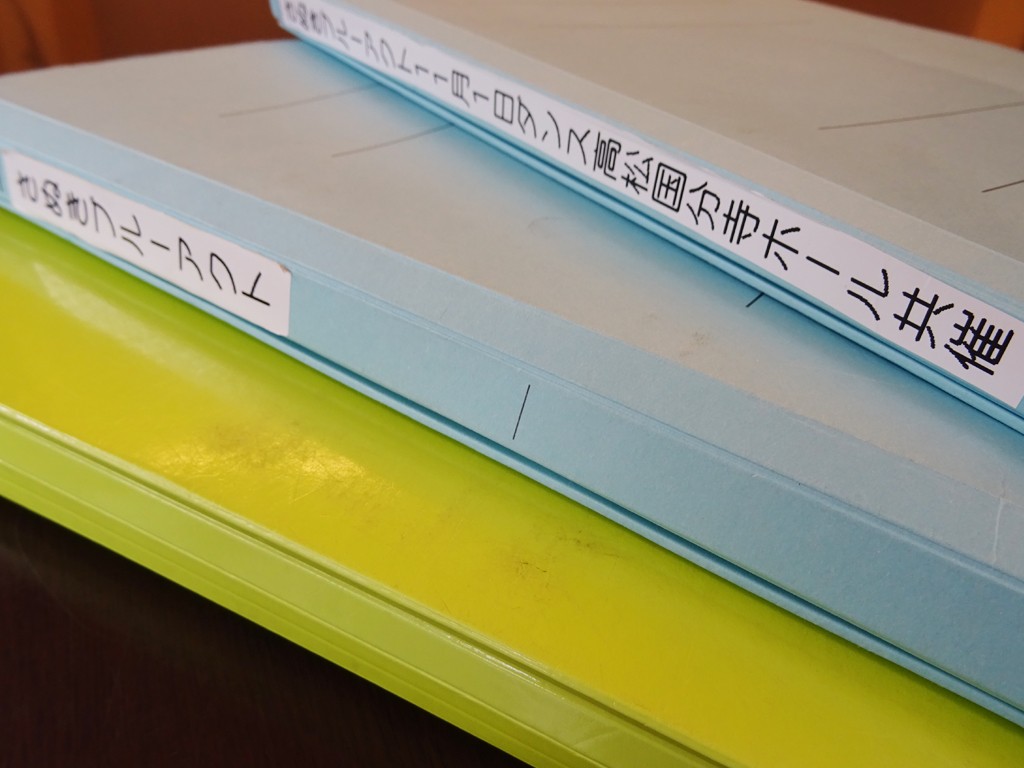
行政への相談、舞台技術者への聞き取り、定款づくり――手探りながらも、実行委員会は着実にその体をなしていきました。
そこに県内の芸術団体や識者からの支援や助言、賛意があったことは言うまでもありません。古宇田さんが活動を始めたのは今年の4月。わずか4か月後の8月には、主催公演の準備に取り掛かるまでになっていました。
アーティストと裏方が支え合う関係が、これまで以上に明確に

11月の主催公演「The Entertainment of dancing world」を経て開かれた、今回の「誰もいないコンサート」。合唱やダンスなど17の芸術団体、6つの制作会社が集結したのは、換気の行き届いた屋外空間でした。
会期は2日間とゆとりをもたせ、観客も団体ごとの総入れ替え制を採用。検温やフェイスシールドの着用など、万全の体制を整えました。とはいえ、状況が状況だけにイベントの告知については、ギリギリまで悩みの種だったといいます。
「私、本当に広報が下手くそなんですよ。コロナ禍なので、下手にやると目につきすぎていかんのかなって」
逡巡を繰り返した古宇田さんは、開催の1週間前になってようやく腰を上げました。

そして迎えた当日。四国一の高さを誇る高松シンボルタワーの吹き抜けスペースには、重厚な舞台が設営されていました。プロフェッショナルによる豪華な音と光の演出に、出演者からは「え、こんなにしてもらったん?」という反応まで。

出演団体からの会費と県からの助成金のみで実現したイベントは、裏方スタッフがこれまで培ってきながらも、発揮する場を失っていた技術を存分に披露する場でもあったのです。
「『僕たちは出演する側を支える立場、支えられるのはおこがましい』って考えなんです」
古宇田さんの言葉を借りれば、今回のイベントには裏方さんへの支援の色合いはありません。ただ、ひとつ確かなのは、立場の違いこそあれど地方に根差して芸術に関わる人たちの関係性が深まったこと。

他府県から技術スタッフを呼ぶことも可能ですが、同じ土地に暮らす者同士でつくり上げる芸術には、きっとそれ以上の深みがあるはずです。
そんな互いの支え合いがあって初めて、地方の舞台芸術は成り立つ。そのことを浮き彫りにしたのが、さぬきブルーアクトの果たした大切な役割だったといえるでしょう。

さて、気になるのがさぬきブルーアクトの今後です。古宇田さんは「残す必要があるっておっしゃる方はいるんですけど」としながらも、活動の終了を示唆していました。
今後、同様の形でコンサートを開くことは可能ですが、ワクチンの普及などが進んだ先には、また以前のような自主公演ができる日常が戻ってくるはず。
「今回がピークだと思って。日常にみんな、帰っていってもらいたい。どっちかって言うたらね」

そう語る古宇田さん。さぬきブルーアクトという営みがつないだアーティストと裏方スタッフとの絆は、地方の舞台芸術にとってすてきなモデルケースになることでしょう。


